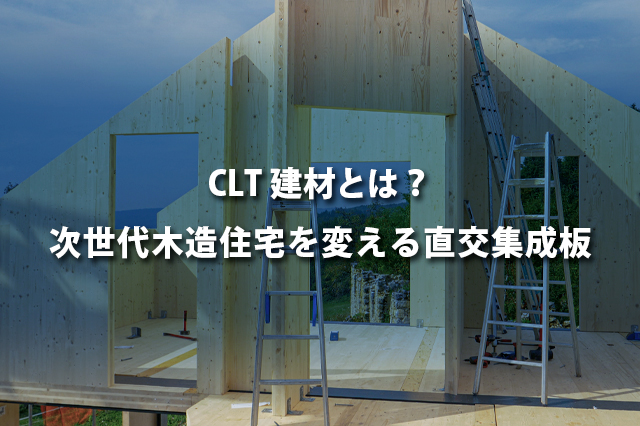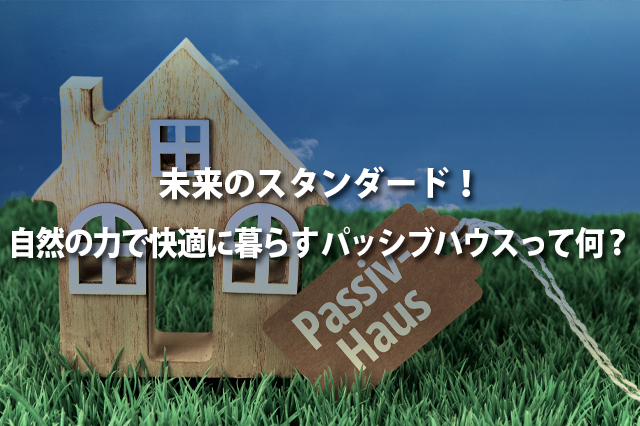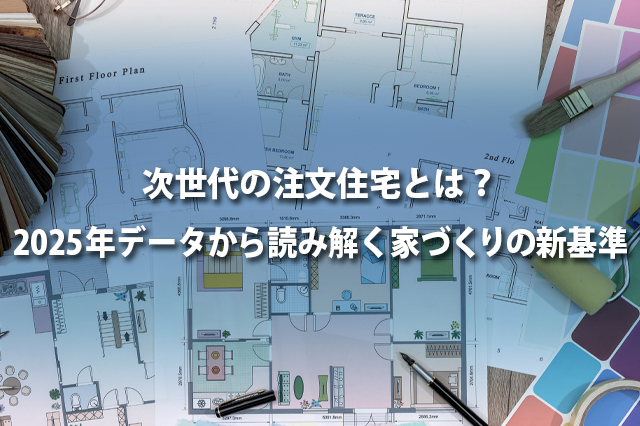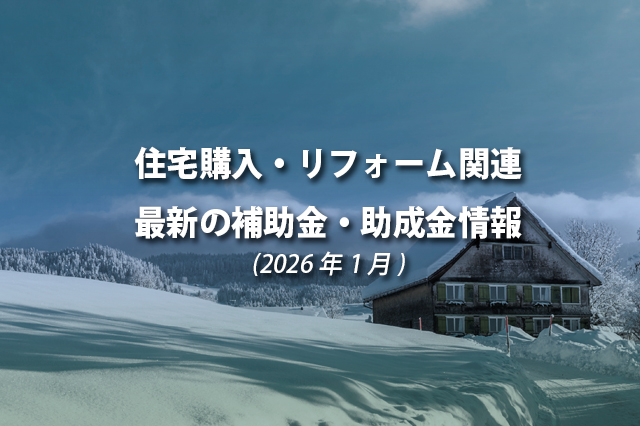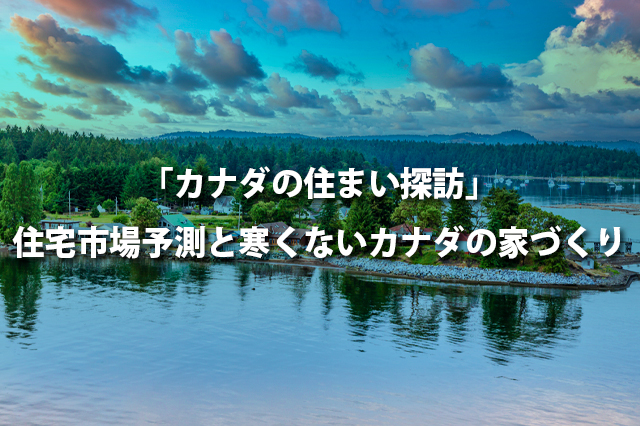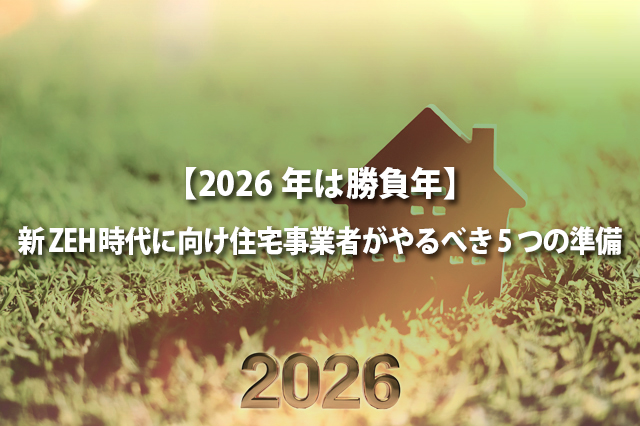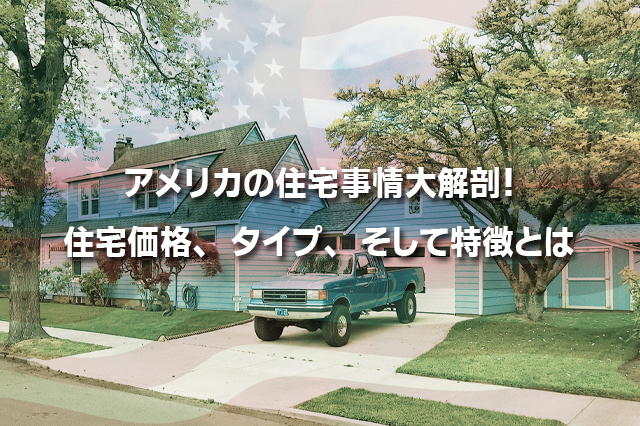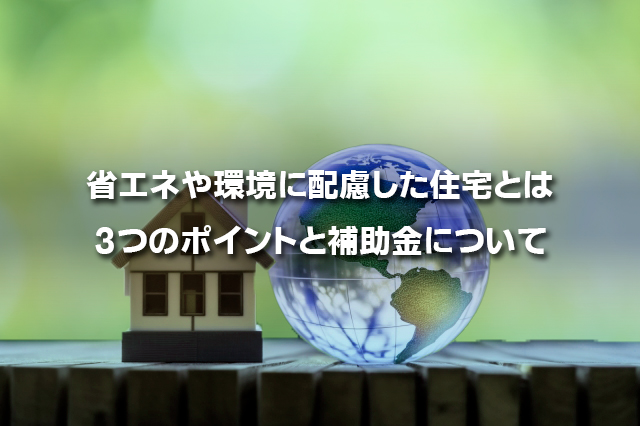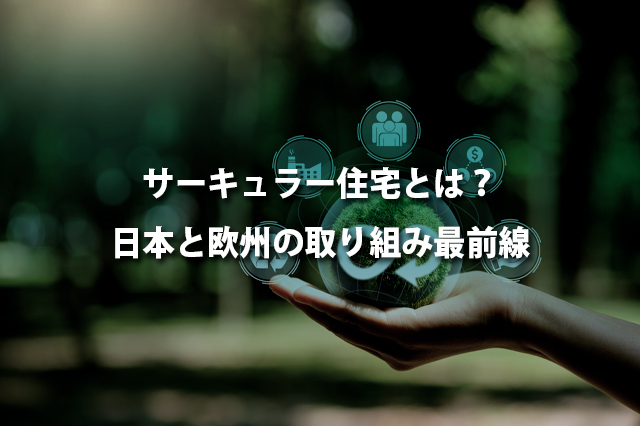
サーキュラー住宅とは?
日本と欧州の取り組み最前線
サーキュラー住宅とは何か、その仕組みや未来性について知りたい方のために、このブログでは基本の概要から最新の海外事例、日本企業の取り組みなど解説します。
サーキュラーエコノミー(循環型経済)の理念を住宅にどう応用し、資源の持続可能な利用を実現するのか、そのメリットとともに現状の課題も明らかにします。
今回のブログを読むことで、サーキュラー住宅が環境に優しく、コスト面や設計の工夫も理解でき、未来の住宅の新たな選択肢が見えてきます。
持続可能な社会づくりに関心がある方や、住宅の新しい潮流に興味がある方にとって、非常に役立つ内容となっています。
(1)サーキュラー住宅とは? 循環型住宅の取り組みと課題
「サーキュラー住宅」とは、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の考え方を住宅に応用した、新しい住まいの概念です。
従来の住宅づくりが「製造 → 使用 → 廃棄」といった直線的(リニア型)の流れを前提としてきたのに対し、サーキュラー住宅は建設資材を繰り返し循環させることを前提とします。
つまり、「設計 → 使用 → 解体 → 回収 → 再利用 → 再設計」という循環ループを住宅のライフサイクルに組み込むことで、廃棄物そのものを極限まで減らし、資源を持続的に活用する仕組みです。
サーキュラーエコノミーは「Circular(円形の)+ Economy(経済)」が示す通り、廃棄を前提としない循環型の経済モデルです。この考え方を建築・住宅に取り入れることで、資源の再利用、再生材の活用、長寿命化といった変革が期待されています。
■サーキュラー住宅ー日本企業の先進的取り組み
日本ではサーキュラー住宅の取り組みはまだ初期段階ですが、すでにいくつかの企業が本格的な実証に進み始めています。
積水ハウスの「循環する家(House to House)」、日建設計が提唱する「Circular Architecture」、竹中工務店によるサーキュラー建材の開発やアップサイクルの取り組みなどがその代表例です。
ここでは、その中でも特に先進的と言われる積水ハウスの事例をもとに、取り組み内容を整理します。
①部材を徹底的に見直すー3種類の循環型部材で構成
積水ハウスは、住宅を構成する3万点以上の部材をすべて見直し、
「リサイクル部材」、「リユース部材」、「リニューアブル部材」の3種類に分類して再構成しています。
・リサイクル部材:主要素材にリサイクル原料を含む部材
・リユース部材:再使用を前提に設計された部材
・リニューアブル部材:バイオマスなど再生可能資源からつくられる部材
この3分類により、住宅そのものを“循環可能な素材の集合体”として設計することを目指しています。
②ゴミを出さない仕組みづくり ー「ゼロエミッションシステム」
新築時の施工現場やアフターメンテナンスによって発生する廃棄物をすべて回収し、全国に整備された「資源循環センター」で細かく分別します。
その分別数はなんと 60~80種類に及び、最終的には100%リサイクル(単純焼却・埋立ゼロ)を実現する仕組みを構築しています。
住宅の建設プロセスそのものを“廃棄物ゼロ”に近づける大胆な取り組みです。
③同じ素材に戻すー水平リサイクルの推進
リサイクルには「別の製品に生まれ変わる」だけでなく、同じ製品として再生する“水平リサイクル”もあります。
積水ハウスは、給水給湯の樹脂配管や畳の下地材などで水平リサイクルを実現し、サプライヤーと協力して製造から廃棄・回収までの循環を一つのループとして成立させています。まさに、住宅の素材が「行って戻ってくる」サーキュラーシステムです。
④長く使える家をつくるー高耐久化と長寿命化
高耐久の建材や工法を採用することで、住宅の寿命そのものを延ばしています。
メンテナンスのしやすさにも配慮されており、建て替えに伴う資源消費やエネルギー負荷を抑えることができます。
“長く使える家=廃棄物を減らす家”という考え方が根幹にあります。
⑤サーキュラー住宅の本質ー経済システム全体を「循環前提」で設計する
サーキュラー住宅は、単に建材をリサイクルする仕組みではありません。
設計・建設・利用・改修・解体という住宅のライフサイクル全体と、そこに関わる経済システムまで含めて“廃棄物や汚染を出さない”ように再構築する考え方です。
言い換えると、「廃棄物を前提としない経済の仕組み」そのものを住宅から再設計する取り組みであり、日本でもその第一歩が始まっている段階だと言えるでしょう。
■サーキュラー住宅の導入メリットや問題点
サーキュラー住宅には、以下のような利点があります。
①資源を無駄にしないー資源効率の向上
サーキュラー住宅の大きな特徴は、建築部材を再利用・再循環させることで、できるだけ新しい資源の使用を減らせる点です。
これにより、将来的な資源の枯渇リスクや価格変動への不安を軽減でき、持続的な資源利用につながります。
②環境に優しい住まい ーCO2削減・廃棄物の減少
リサイクルや再利用を前提にした住宅づくりは、製造や廃棄に伴うCO?排出量の削減に貢献します。
また、廃棄物そのものを減らせるため、埋立地や焼却施設の負荷も軽くなり、環境全体への影響を抑えることができます。
③経済面でもメリットー付加価値創出と長期的なコスト削減
廃材を「アップサイクル」して新たな価値を持つ素材として活用することで、経済的な価値が生まれます。
さらに、長寿命化や再利用を前提とした設計を採用することで、長期的にみると資材コストの削減につながる可能性もあります。
④将来への適応力が高いーモジュール化と分解しやすい設計
サーキュラー住宅では、解体や再配置をしやすくする「分解を前提にした設計(Design for Disassembly)」が取り入れられます。
また、モジュール構造を採用することで、家族構成の変化やライフスタイルの移り変わりにも柔軟に対応できるため、長く使い続けられる住宅となります。
⑤企業・地域にも良い影響ーブランド価値の向上と差別化
環境配慮型の取り組みは企業や施工会社のイメージ向上につながり、サステナビリティを重視する顧客からの信頼も得やすくなります。
また、サーキュラー住宅は「持続可能なまちづくり」の先進例として注目されやすく、市場での差別化や企業成長のきっかけにもなります。
■サーキュラー住宅が抱える5つの壁
サーキュラー住宅は注目されながらも、まだ市場として本格的に成立していません。
その背景には、導入に向けて乗り越えるべき多くのハードルが存在します。ここでは、その主な課題をわかりやすく整理します。
①コストの高さー回収・分別・再加工に費用がかかる
サーキュラー住宅は理念として高く評価され、制度整備も少しずつ進んでいます。
しかし現状では、循環型部材を扱うには多くのコストがかかります。
部材の回収・分別・再加工には手間と費用がかかり、サーキュラー建材そのものも市場規模が小さいため価格が高く、選択肢も限られています。
結果として、一般的な住宅よりも初期コストが高くなりやすい点が大きな壁になっています。
② 技術的ハードルー分解設計や品質管理の難しさ
サーキュラー住宅では“解体しやすい設計”を前提としますが、これには高度な設計知識と経験が求められます。
さらに、再利用部材は品質や性能にばらつきが出るため、それをどう管理するかも大きな課題です。
現在は、部材の来歴を管理する「マテリアルパスポート」の導入が検討されていますが、運用には時間とコストがかかるため、技術面の課題は依然大きいと言えます。
③ 制度・法規制の未整備ー安全基準や責任区分の課題
建築分野ではようやくサーキュラー建材を評価する基準づくりが始まった段階です。
しかし、建築廃材の再利用に関する規制、安全性の基準、リユース部材を用いた場合の責任範囲など、制度面での課題が多く残されています。
市場が拡大するためには、行政・業界・企業が協力して法的枠組みを整えていく必要があります。
④ サプライチェーンが未成熟ー産業全体の協働が必要
循環型資材や再利用建材の供給体制はまだ安定しておらず、市場としても成熟していない状況です。
そのため、サプライヤー、設計者、建築会社が一体となり、協働しながらサーキュラー住宅のための標準化や流通網を整える必要があります。
現状では、その基盤整備がまだ不十分と言えます。
⑤ ユーザー側の理解がまだ低い ― 中古部材への抵抗感
サーキュラー住宅には「中古部材を使う家」というイメージがつきまとい、購入者が不安を感じることもあります。
また、設計段階から解体・再利用までを見据えていること自体が理解されにくく、価値が伝わりにくいという課題もあります。
特に新築住宅購入では初期コストが重視されやすいため、長期的なメリットをどう伝えるかが普及の鍵になるでしょう。
■まとめ:サーキュラー住宅への第一歩
サーキュラー住宅は、単に「エコな家」をつくる取り組みではなく、住宅の在り方そのものを根本から再設計する壮大なプロジェクトです。
しかし、制度・技術・コスト・市場理解など、実現のためには解決すべき壁が多いのも事実です。
だからこそ、「完璧なサーキュラー住宅」を一足飛びに目指すのではなく、まずは廃棄物削減や水平リサイクルなど、取り組みやすい部分から段階的に進めることが現実解だと感じます。
海外の先行事例を参考にしながら、日本の気候・産業構造・住宅文化に合った循環型住宅モデルを育てていく。その積み重ねこそが、未来の住宅産業を持続可能な姿へと変えていく最初の一歩なのではないでしょうか。
参考:
積水ハウス:「循環する家」
サーキュラーエコノミーとは? 3原則やメリット・デメリットを解説!
(2)欧州がリードするサーキュラー住宅の取り組み
サーキュラー住宅とは、循環経済(サーキュラーエコノミー)の理念である「リデュース・リユース・リサイクル」をさらに発展させ、建築資源を無駄なく循環させることで持続可能な社会を実現しようとする住宅モデルです。
単なる環境対策にとどまらず、企業や地域の成長戦略としても注目され、世界中でその取り組みが加速しています。
■万博を舞台に実証が進むー大阪・関西万博でのサーキュラー建築の実証
日本でもサーキュラー建築の実践が進みつつあります。
大東建託は、万博の「ポップアップステージ(東内)」に使用した国産材を、47都道府県それぞれの建築プロジェクトで再利用すると発表。
単なる“リサイクル”ではなく、社会全体で資材を循環させる仕組みを示しました。
また、日本館で使用されたCLTパネルは、江東区東雲にある「ROOFLAG賃貸住宅未来展示場」に移設され、展示モニュメントやノベルティへと姿を変えて再活用されています。
■ヨーロッパで進むサーキュラー住宅の最前線
ヨーロッパでは、政府・自治体がサーキュラーエコノミーへの移行を政策レベルで強力に推進しています。
建設業はその主要ターゲットであり、住宅分野も大きく変革を迫られています。
・EU「サーキュラーエコノミー行動計画(CEAP)」:
2020年に採択されたCEAPでは、製品の耐久性・修理性・リサイクル性の向上が義務化に向けて進み、住宅設備や建材にも影響が及んでいます。
・フランスの「修理可能指数」義務化:
2021年1月以降、家電製品に修理しやすさを示す「修理スコア」の表示が必須となり、住宅設備の長寿命化を後押ししています。
・ベルギーなどでの「パッシブハウス基準」義務化:
新築建物に超省エネ基準を求めるなど、エネルギー効率もサーキュラーエコノミーの一環として強化されています。
ヨーロッパは世界的にもサーキュラーエコノミーの推進力が強く、その姿勢は住宅・建築の分野にも明確に表れています。
ここではオランダ、デンマーク、ドイツ、ベルギーの4カ国について見てみましょう。
① オランダ:2050年「完全サーキュラー」へ向けた国家プロジェクト
(2030年までに一次原材料の使用量50%削減)
オランダはEUの中でも特にサーキュラーエコノミーに積極的で、2050年までに「100%サーキュラー国家」を実現するという野心的な目標を掲げています。
建築分野はその中核として位置づけられ、さまざまな実証プロジェクトが進められています。
代表的なのが、循環型建築スタジオによって制作された「People’s Pavilion」です。
これはイベント用のパビリオンとして建設されましたが、“壊すことを前提に建てる”という思想のもと、市民や企業から提供された資材を、極力改変せずに利用しています。構造部材はネジや紐で固定され、イベント終了後には完全解体し、すべての部材を元の所有者へ返却するという、徹底した循環モデルが実証されました。
この事例は、サーキュラー建築が「環境配慮」だけでなく、「資材の借り入れ・返却」という新しい経済活動の可能性を持つことを示したプロジェクトでもあります。
② デンマーク:「Circle House」ーすべての部材を分解・再利用できる住宅
(2020年完成:60戸の循環型社会住宅)
デンマークの「Circle House」は国内初の循環型社会住宅として、国際的にも高い評価を受けています。
オーフス郊外に建設された60戸の住宅で構成され、建物の構造・部材はすべて分解して他の建築物に再利用できるよう設計されています。
特徴的なのは、使用される建材がすべてデジタル化され、「マテリアルパスポート」として管理されている点です。
これにより、将来の改修・解体時に、どの部材がどこに使われており、どのように再利用できるかが一目で把握できます。
また、工法にも特徴があり、ボルト固定や組立式のモジュールを利用することで、短時間での組立・解体が可能となっています。
「循環性を高めつつ、住宅としての住み心地も損なわない」ことを実証した代表的なプロジェクトです。
参考:サークルハウス
③ ドイツ:「Circular Tiny House CTH*1」──廃材×自然素材によるゼロ廃棄住宅
ドイツでは大学や教育機関によるサーキュラー建築の試みが盛んで、その象徴が「Circular Tiny House CTH*1」です。わずか19㎡の小さな住宅ですが、建材はすべて廃材・自然素材・地域資源のいずれかで構成されています。
例として、
・害虫被害を受けた木材
・解体現場から回収した窓
・藁、粘土などのローカル自然素材
といった素材を組み合わせ、高い断熱性と快適性も両立しています。
さらに驚くべき点は、「接着剤や釘を一切使わない」点です。
電動ドライバー一本で解体でき、部材を再び別の建築物に再利用できる構造となっています。
これは大学院生たちが実際に設計・施工したプロジェクトであり、教育と実践が結びついた新しい循環型建築の形と言えるでしょう。
参考:【海外事例】ドイツ発・循環型社会をかたちにする、小さな実験住宅「Circular Tiny House CTH*1」
④ ベルギー:建材のライフサイクルを「見える化」し、再利用を徹底する国 (Mundo Group の先進的な取り組み)
ベルギーでは、建材のライフサイクル分析(LCA)が普及し、設計段階から「どれほど循環性が高い建物か」を評価する仕組みが整いつつあります。
不動産開発企業「Mundo Group」はその中でも先進的で、建材を積極的に再利用したパッシブハウスを多数開発。
その結果、建築にかかるエネルギー消費を90%以上削減したプロジェクトも実現しています。
また、建材の循環利用を促進するための無料ソフトウェアが国内で広く使われており、
「循環性を考えながら設計すること」が当たり前の文化として根付いています。
参考:建材の再利用でエネルギー9割削減。ベルギー発の不動産開発「Mundo Group」【欧州CE企業 Vol.4 】
■まとめ:サーキュラー住宅の未来
サーキュラー住宅は、単なる環境対策ではなく、「産業構造を根本から変える大転換」 と言える段階に入っています。
日本では大手企業が動き始めたばかりですが、欧州では政策・教育・技術が連動し、すでに社会全体で循環型建築が実証されるフェーズに達しています。
それに比べると、日本はようやくスタートラインに立った状態ですが、その分、海外事例という“教科書”を活かしながら最短距離で発展できるという強みもあります。
今後は「建材の標準化」、「分解可能な設計の普及」、「建築業界全体での協働」、「中古資材への抵抗感を減らすユーザー教育」といった課題をひとつずつクリアした先に、真のサーキュラー住宅市場が形成されるでしょう。
2030年までに世界では約700兆円、日本では80兆円規模の市場が予測されています。
“廃棄物ゼロ”の未来は、もはや理想ではなく、取り組み次第で確実に実現可能な目標です。
そして、日本の建設業界にとっては、「環境 × 経済 × 技術革新」を同時に達成できる、数十年に一度の大きなチャンスと言えるでしょう。
- 最新のトピックス
- 人気のトピックス