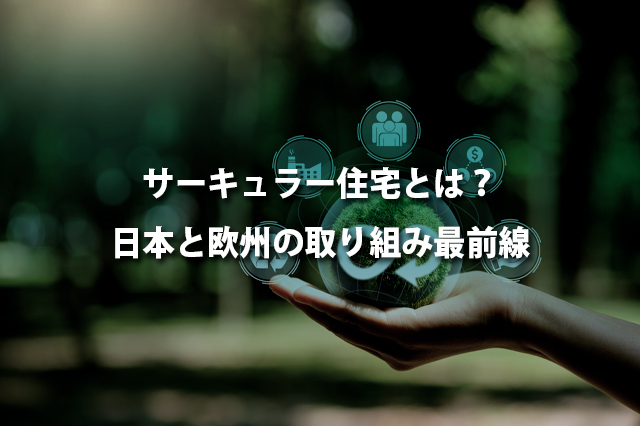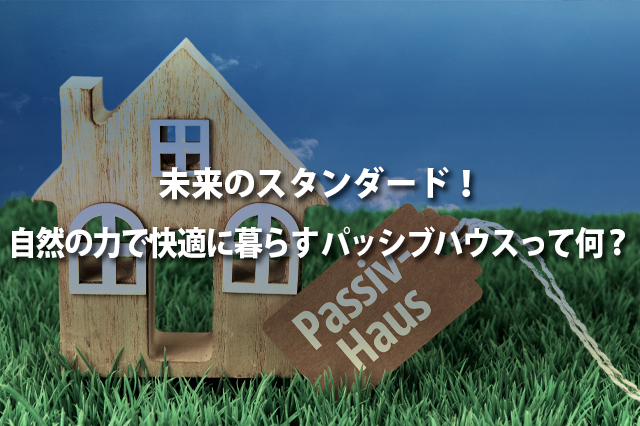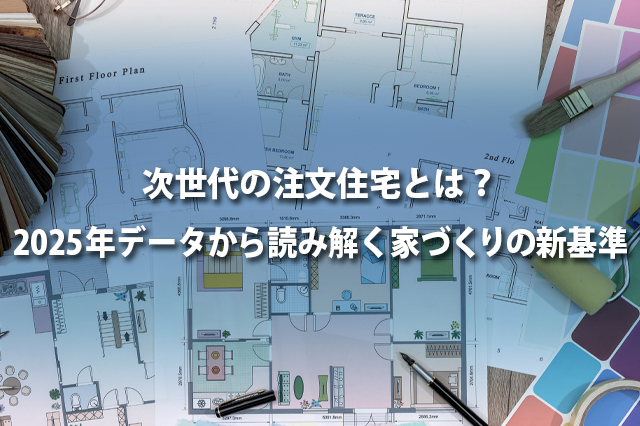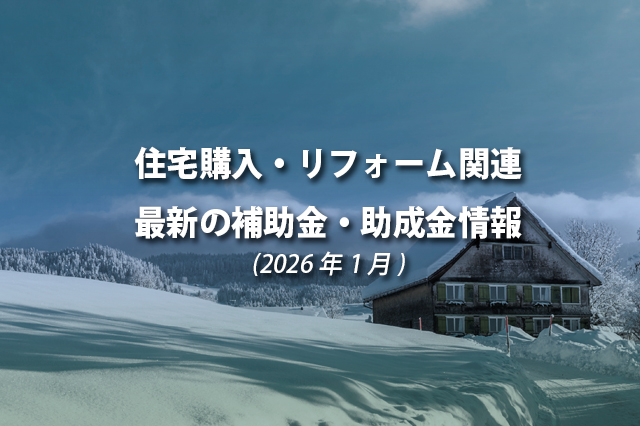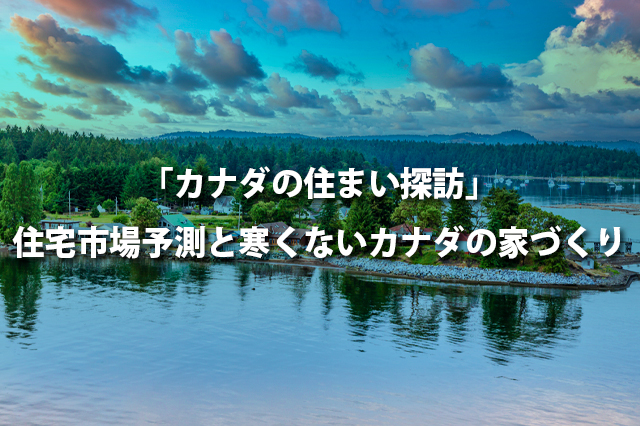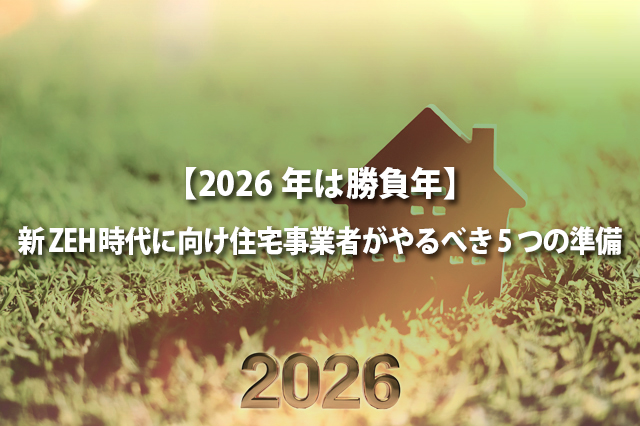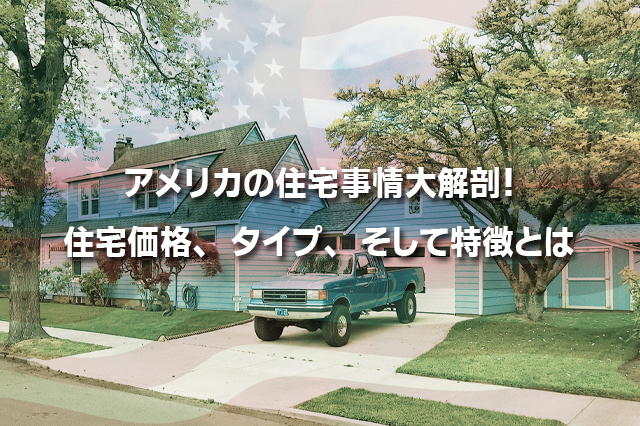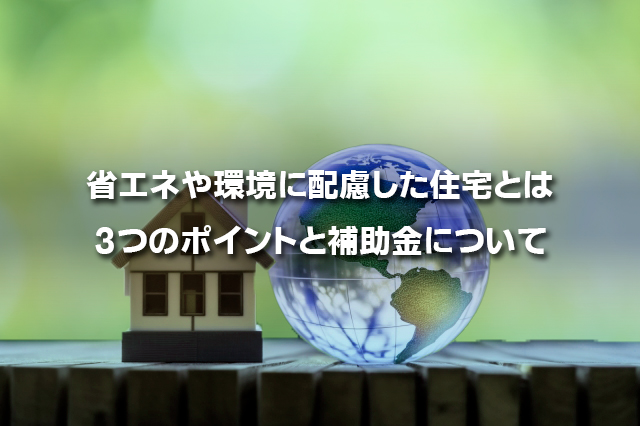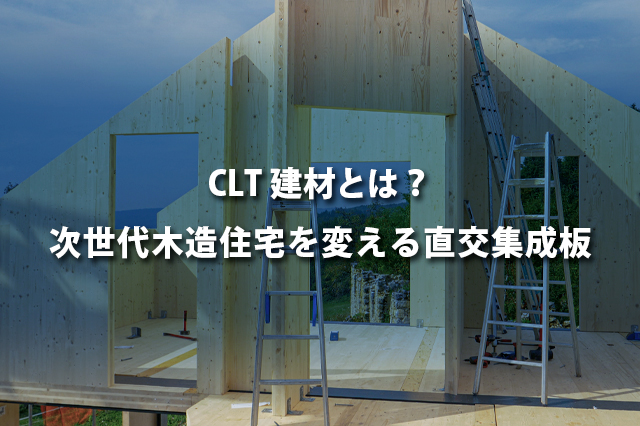
CLT建材とは?
次世代木造住宅を変える直交集成板
近年、いま注目を集めている次世代木質建材「CLT(直交集成板)」をご存じでしょうか。
CLT建材は、木の強さと軽さを活かした新しい木造建築の形として、住宅から中・大規模建築まで急速に普及が進んでいます。
今回のブログでは、このCLT建材の仕組みや特徴、CLT住宅の最新動向、そして国や自治体による補助金・支援制度までをわかりやすく解説します。
さらに、国産材の活用による林業再生や、サステナブルな家づくりへの貢献についても掘り下げます。
「木で建てる未来の家」に興味のある方に、必読の内容となっています。
(1)CLTが切り拓く建築と林業の未来
■CLT建材とは
CLT(Cross Laminated Timber、直交集成板)は、日本の林業と建築業界に革新的な変化をもたらす次世代の木質建材として注目を集めています。
CLTは木材の繊維方向を直交させながら積層・接着することで、従来の木材では実現できなかった高い強度と寸法安定性を備えています。
国内では最大で12m×3m、厚さ36~300mmの原板が製造可能で、住宅から大規模建築まで幅広く対応できます。
CLTの主な特性は以下の通りです。
- 軽量性:鉄筋コンクリートの約1/5の比重
- 高強度:直交構造により曲げやねじれに強い
- 大型化:最大12m×3m、厚さ270mm(9層)まで製造可能
- 高断熱性:木材の自然な断熱性能を発揮
- 耐火性:厚い木材は表面が炭化層となり、内部を守る
- 高耐震性:軽量かつ強固な構造体が地震に強い
上記特性を生かした建築法が「CLT工法」と呼ばれます。
パネル状のCLTを壁や床、屋根として組み上げるパネル工法が主流で、まるで積み木やブロックを積み上げるように建物を構成します。
特に、共同住宅やホテル、オフィスビルなど、壁構造の多い用途に適しています。
CLTは1994年にオーストリア・グラーツ工科大学のゲルハルト・シックホーファー教授らによって開発され、いまや世界中で普及が進んでいます。
日本でもその流れは加速しており、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会では選手村の更衣室ロッカーやベンチ、屋外エレベーターの外壁などに採用されました。
さらに、今年、2025年大阪・関西万博では日本館にもCLTが用いられ、国産木材の可能性を世界に発信する象徴的なプロジェクトとなっています。
建築家の隈研吾氏をはじめとする著名な設計者たちは、CLTの「軽さ」「強さ」「温もりある質感」を生かした建築を全国各地で展開中です。
こうした動きは、木材利用の促進や脱炭素化に貢献し、次世代の木造建築のスタンダードを形づくっています。
最新の統計によれば、2024年時点で国内のCLT建築物は1,300件を超え、2025年度の完成予定件数は前年度比116%増の311件と、急速な成長を遂げています。
■CLT普及がもたらす林業の再生とSDGsへの貢献
CLTの普及は、単なる建築技術の進化にとどまりません。
日本の林業を再び活性化し、持続可能な社会を築く鍵としても注目されています。
戦後に植えられたスギやヒノキが伐採期を迎える中、採算性の低下や人手不足によって手入れの行き届かない森林が増えています。CLTは小径木や間伐材も活用できるため、これまで利用が難しかった木材に新たな需要を生み出します。
これにより、地域の製材業者や林業従事者の収益改善、地域経済の循環にもつながります。
また、木材は生育中にCO2吸収し、建物として使用されることでその炭素を長期間固定します。製造時のCO2排出量も鉄やコンクリートより格段に少なく、建築全体の環境負荷を大幅に削減します。
このような取り組みは、国連のSDGs(持続可能な開発目標)の中でも以下の項目に深く関わります。
- 目標12:つくる責任 つかう責任
- 目標13:気候変動に具体的な対策を
- 目標15:陸の豊かさも守ろう
国産CLTの活用は、環境・経済・社会の三側面を同時に支える“循環型社会”の構築に向けた大きな一歩といえるでしょう。
■まとめ
私たちはこれまで、鉄とコンクリートの時代を「近代建築の象徴」として歩んできました。
しかし、いま求められているのは“成長する建築”、つまり「自然と共に生きる建築」です。
CLTは、単なる新素材ではなく、「木の時代」を都市に取り戻すための道具となり得ます。
高層ビルが木で建てられる未来、子どもたちが木のぬくもりに囲まれて育つ学校、地域の木で地域の建物をつくる好循環。
そのすべてが、CLTによって現実のものになりつつあります。
建築が自然に還るという発想が、これからの社会をデザインする原点になるのではないでしょうか。
(2)CLT住宅はどこまで来た? 普及の壁と国の支援
CLTは、これまで公共施設やオフィスビル、ホテルなどの中・大規模建築での採用が進んできました。
では、私たちの身近な「住宅」への普及はどうなっているのでしょうか。
近年では、福岡県筑紫野市で在来軸組構法にCLT36の杉パネルを取り入れた一般住宅、東京都福生市の防火地域で3階建て共同住宅にCLTを使用した事例、神奈川県小田原市のガレージハウスを軽量鉄骨造からCLT構造へリノベーションした事例などが見られます。
このように住宅分野でも採用事例は増えていますが、現状では賃貸住宅や商業施設などの「集合・準公共用途」が中心で、一般の注文住宅や建売住宅での導入はまだ限定的です。
■CLT普及の壁となる課題
・コストと技術のハードル:
CLTを構造材や仕上げ材として用いると、在来木造や軽量鉄骨造に比べて1.3~1.5倍のコスト増になることがあります。価格競争が激しい建売住宅では、このコスト差が大きな壁となっています。
また、CLTは国内では比較的新しい建材のため、設計・施工のノウハウを持つ業者がまだ少ないのが現状です。
設計者や施工者への技術教育、標準的な施工マニュアルや講習会など、現場レベルでの知識共有が今後の普及の鍵を握ります。
・制度・法規上の課題:
防火地域や準防火地域では、CLTの耐火性能を実験や設計で証明する必要があります。
建築基準法や住宅性能表示制度、自治体の条例などにより、認定や申請手続きが複雑化し、設計・審査の負担が大きいという現実もあります。
特に小規模住宅においては、こうした手続きが工期やコストに影響しやすく、普及の足かせになっています。
■普及に向けた改善の方向性
CLTのコストや制度面での課題を乗り越えるには、次のような取り組みが求められます。
・国や自治体による補助金・税制支援の充実:
CLT住宅を建てる施主・事業者に対して、補助金や税優遇を通じた後押しが必要です。
・パネル寸法・接合部仕様などの標準化:
モジュール化を進めることで、設計や加工の手間を削減し、コスト低減が可能になります。
・耐火・防火性能の迅速な認定制度整備:
防火地域での実用化が進めば、都市部の集合住宅にも採用が広がるでしょう。
■国の支援制度と最新の取り組み(2025年度)
・戸建住宅 ZEH化等支援事業:
ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)を対象に、一定量のCLTを使用した住宅には定額90万円/戸の追加補助が受けられます。
ZEHまたはZEH+基準を満たすことが条件です。
・集合住宅の省CO?化促進事業(環境省):
ZEH-M(集合住宅型ZEH)基準を満たし、CLTを使用する新築集合住宅に対し、以下の補助が用意されています。
- CLT使用量に応じて 10万円/m3(上限1,500万円/棟)
- 新築低層・中層ZEH-M:定額40万円/戸(条件により50万円/戸)
- 高層ZEH-M:補助率1/3以内(上限40~50万円/戸)
・林野庁「CLTを活用した建築物等実証事業」:
CLTの設計・施工・コスト検証などを支援する事業で、住宅分野も対象です。
(実施団体:公益財団法人 日本住宅・木材技術センター)
参考:令和7年度 CLT活用建築物等実証事業
・内閣官房「CLT支援制度一覧」:
内閣官房と関係省庁が連携し、CLTを活用した建築物への支援制度をまとめています。年度ごとの助成枠・対象用途が一目で分かる資料が公開されています。
参考:CLTを活用した建築物への支援制度
・政府一元窓口による支援体制:
内閣官房の「CLT活用促進のための政府一元窓口」では、
- 相談窓口(事業者・自治体対応)
- CLT企画・設計相談室
- 実務者向け講習会・技術資料の提供 などを通じて、CLT建築の実現を支援しています。
■まとめ
CLTは、高い「耐震性」「断熱性」「デザイン性」を併せ持つ次世代の木質建材です。
環境負荷を抑えつつ、国産材の活用によって林業の再生にも寄与できる、この素材が住宅分野で広がる意義は非常に大きいといえます。
一方で、CLTの住宅利用を本格的に普及させるには、設計者・施工者・行政が連携し、「標準化」「教育」「コスト低減」の3つを同時に進めることが不可欠です。
特に、住宅メーカーや設計事務所が積極的にCLTを活かした「中価格帯住宅モデル」を新築住宅の購入ユーザーに提示できるようになれば、一般層への浸透は一気に進むでしょう。
CLT住宅の普及は、単なる建材の選択ではなく、日本の森林資源を未来につなぐ社会的選択でもあります。持続可能な木の住まいづくりを、私たち一人ひとりの家づくりから考える時期に来ているのかもしれません。
参考:
- 最新のトピックス
- 人気のトピックス