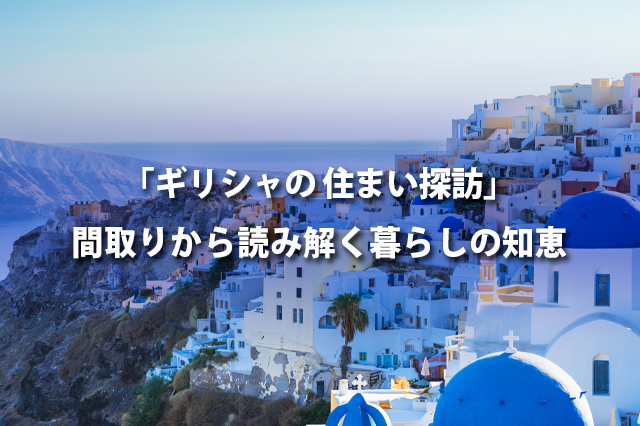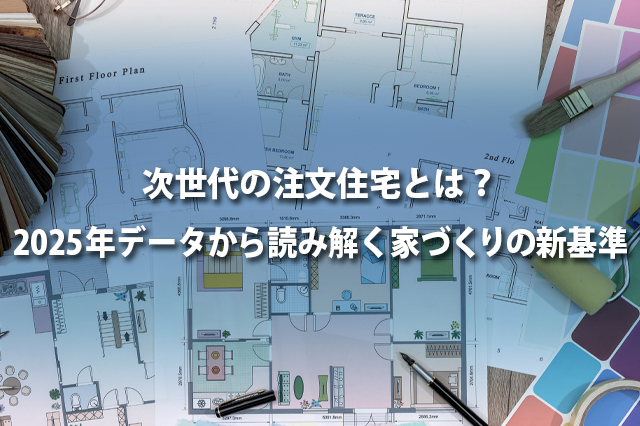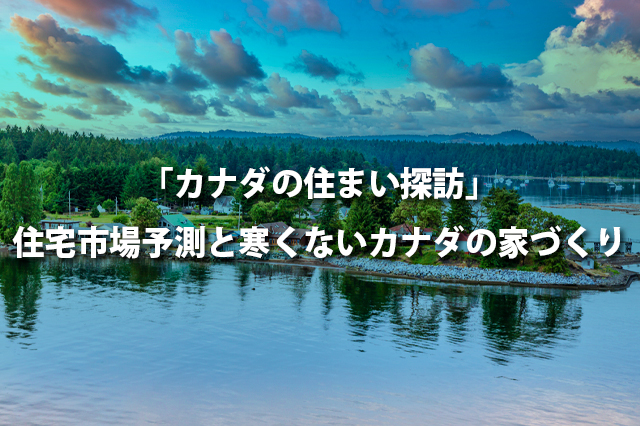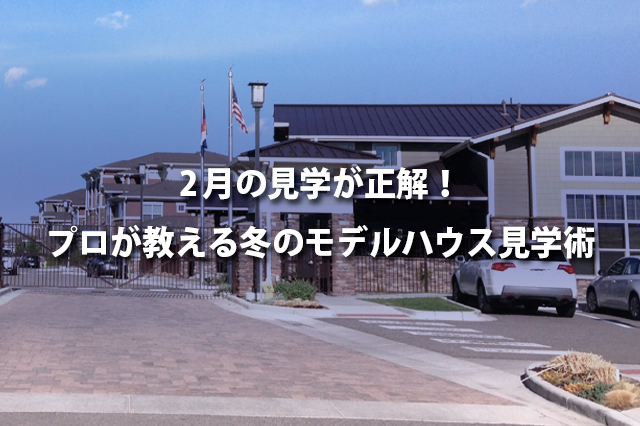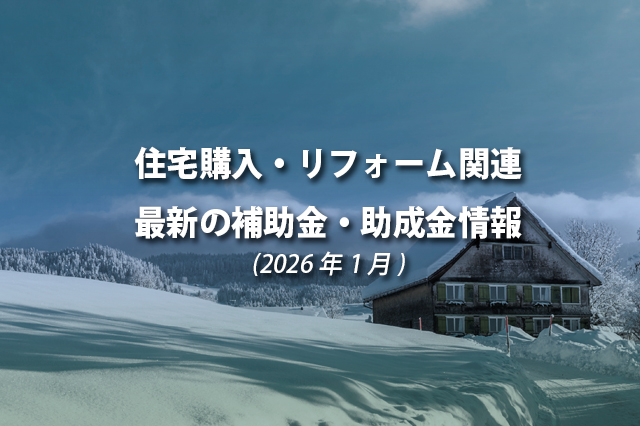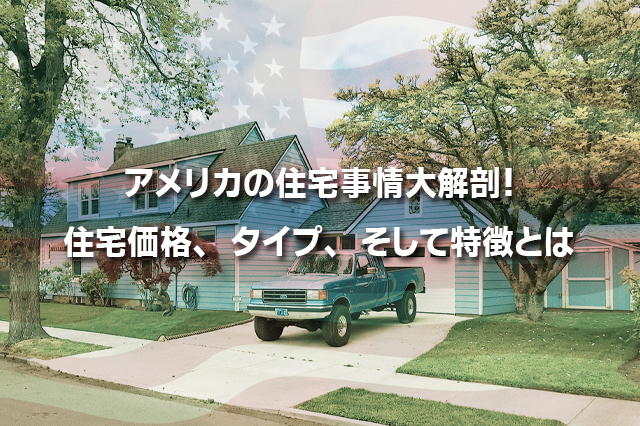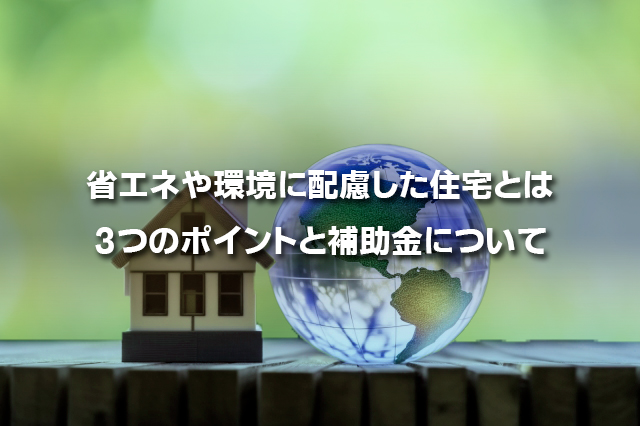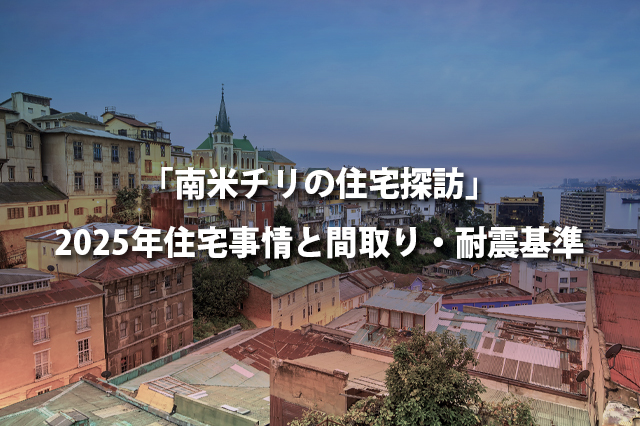
「南米チリの住宅探訪」
2025年住宅事情と間取り・耐震基準
南米チリは、太平洋プレートと南米プレートがせめぎ合う「環太平洋火山帯」に位置し、日本と同様に地震が非常に多い国として知られています。
そんな地震が多い国チリの住宅は、どんな特徴があるのだろう?さらに、日本と同じ南北に細長い国土では、地域ごとに家の形式も変わるのだろうか?
など、このような疑問を持つ方に向けて、今回のブログでは、「チリの最新の住宅市場の動向」、「チリの海辺・山岳・砂漠地帯の間取りの違い」、「世界有数のチリの建築耐震基準」を徹底解説します。
チリの家づくりには、「自然との共生」や「命を守る設計」など、日本の住宅設計にも応用できる知恵が詰まっています。
この記事を読むことで、チリ住宅の実像と、そこから学べる「住まいづくりの新しい視点」が得られるでしょう。
(1)2025年のチリ住宅事情を徹底分析
2025年現在、南米チリの住宅市場は価格上昇の傾向が続いています。
住宅価格指数によると、2025年6月には160.90ポイント(前月比+0.90%)と上昇しており、上昇率も加速しています。
こうした動向の背景には、建設コストの高騰・供給不足・都市部への人口集中といった要因が複合的に影響しています。
住宅市場を読み解くうえで重要なのは、「住宅ローン金利と利用しやすさ」、「供給・建設コスト」、「賃貸市場」、「地域差」、「住宅価格と所得のバランス」の5つの視点です。それぞれの内容を見ていきましょう。
■住宅ローン金利と利用しやすさ
2025年現在、チリの住宅ローン金利は約4.3%前後。
政策金利(TPM)の安定化により、前年よりも落ち着いた水準が続いています。
ただし、自己資金や信用審査の基準は厳格化しており、若年層や低所得層にとってはハードルが高い状況です。
一方、チリ政府の住宅補助金制度「Subsidio Habitacional」を活用すれば、初めての住宅購入も現実的になります。こうした支援策が、住宅取得層の拡大に一定の効果をもたらしています。
■供給状況と建設コスト
チリでは依然として需要が供給を上回る状況が続いています。
現在、約11万4,000世帯が非公式居住地(カンパメントス)に住み、4万人以上がホームレス状態にあります。
これを受けて、住宅・都市開発省(MINVU)は年間10~12万戸の住宅供給を目標に掲げています。
一方、建設コストは前年比+6?8%上昇。鉄鋼・木材・人件費の高騰が主因です。
サンティアゴなど都市部では集合住宅(マンション)建設が増加し、郊外では依然として戸建て住宅の人気が根強く続いています。
■賃貸市場の動向
住宅価格の上昇やローン審査の厳格化により、都市部を中心に賃貸需要が急増しています。
サンティアゴ中心部では、賃料利回りが4~6%と上昇傾向にあり、不動産投資の注目度も高まっています。
チリ政府も賃貸補助制度(Subsidio de Arriendo)を拡充し、低所得層の家賃負担軽減に取り組んでいます。
■地域差(都市ごとの特徴)
チリは南北に長い国土を持つため、地域によって住宅市場の状況が大きく異なります。
サンティアゴ首都圏:
全国平均を上回る高価格・高賃料。人気エリアは「ラス・コンデス」や「プロビデンシア」。
北部アンタファガスタ:
鉱山開発の影響で価格高め。投資利回りも高い傾向。
沿岸部バルパライソ:
観光都市。中心部は高値だが、内陸部は比較的手頃。
南部テムコ・アラウカニア地方:
価格はサンティアゴの約6割。自然環境を求める層に人気。
■住宅価格と所得のバランス
2025年のチリ全体の住宅価格は前年比+2~4%上昇しています。
サンティアゴ中心部のマンションは、㎡あたり2,000,000~3,500,000 CLP(約30~50万円)。
地方都市の戸建て住宅は、㎡あたり1,000,000 CLP前後(約15万円)と比較的手頃です。
一方で、チリの月収中央値は1,447,389 CLP(約22万円)。
日本に比べると所得に対する住宅価格の負担はやや軽く、適正な価格感覚が維持されています。
2025年のチリ住宅市場は、価格上昇の継続、金利の安定化、賃貸需要の増加、地域間格差の拡大という4つのキーワードで整理できるでしょう。
サンティアゴでは依然として高価格帯が続いていますが、地方都市ではまだ手頃な価格での住宅取得が可能です。
また、政府の補助制度や住宅供給政策の進展によって、今後は住宅取得のチャンスが広がる可能性もあります。
(2)南北に細長い国、チリの住宅間取りの特徴
南米大陸の西側に位置するチリは、南北に約4,300キロメートルも伸びる細長い国。海岸線、山岳地帯、砂漠地帯と、気候や地形が大きく異なるため、地域ごとに住宅の造りや間取りにも明確な違いが見られます。ここでは、代表的な3地域の特徴を整理してみましょう。
■「海岸線沿いの住宅(チリ中央部)」
太平洋沿いや湖沼地帯に建つ住宅は、開放的な間取りが特徴です。
大きなガラス窓やテラス、中庭を取り入れ、海や自然の風景、光や風を感じられる空間が好まれます。敷地の傾斜を活かした配置計画も多く、都市部に比べて「外とのつながり」を重視する傾向があります。
また、首都サンティアゴから約100kmの港町・バルパライソでは、外壁をカラフルに塗った個性的な家が立ち並びます。この街並みは2003年、「バルパライソの海港都市とその歴史的な町並み」として世界遺産にも登録され、チリらしい住宅文化の象徴となっています。
■「アンデス山脈沿いの住宅(山岳地帯)」
アンデス山脈沿いの住宅では、断熱性・耐寒性を重視。石やレンガなど重厚な自然素材を使い、厳しい寒さに対応しています。
開放的な間取りよりも、プライバシーを確保し、個室を分ける構成が多く、家族が集うリビングには暖炉を設けるなど、小規模ながら暖かみのあるコミュニティスペースが特徴です。
■「アタカマ砂漠の住宅(北部乾燥地帯)」
世界でも有数の乾燥地帯・アタカマ砂漠では、遮熱・断熱・通風を重視したパッシブデザインの住宅が主流です。
窓を小さく設け、閉じた構成や日陰を多くつくる動線設計で、過酷な気候に対応します。開放的な間取りは少なく、省エネ性と耐久性を両立した機能的デザインが特徴です。
■チリ住宅に共通する間取りの傾向
地域によって様々な特徴を持つチリの住宅ですが、伝統的な要素や文化的な共通点も存在します。
中央パティオ(中庭)型:
伝統的なチリ住宅は、中央に庭を配した回廊型の間取りが特徴です。中庭には噴水やヤシの木を植え、自然との調和と癒しの空間を演出します。
東向きの玄関:
チリの先住民族・マプチェ族の伝統に従い、玄関を朝日が昇る東向きに設けることが多く、太陽を生活の中心とする文化が息づいています。
キッチン中心の設計:
チリの住宅では、キッチンが家の中心空間として重視されます。
アイランド型の広いキッチンに家族が集い、リビングや外部テラスへとアクセスしやすい配置が主流です。
すべての部屋にキッチンからアクセスできるよう設計され、家族の交流を生む間取りといえます。
プライベート空間の分離:
寝室や書斎、浴室などのプライベートゾーンは、リビングから離れた建物の反対側や上階に配置され、静かな時間を確保します。
光と風を取り込む設計:
吹き抜けや天窓、ハイサイドライトを用いて自然光を積極的に取り入れ、大きな開口部で屋外と一体化する光と風の設計が重視されています。
チリの住宅は、「自然と共に暮らす」という思想が地域性と融合し、実に多彩な間取りを生み出しています。
海辺では風と光を、山岳地では断熱と暖を、砂漠地帯では省エネと遮熱を。それぞれの土地の知恵と文化が、空間デザインに息づいています。
こうしたチリの住宅は、日本の住宅設計にも多くのヒントを与えてくれます。
例えば、気候風土に合わせた素材選び、中庭や吹き抜けを活かした採光・通風設計。
さらにキッチン中心の間取りなどは、日本の暮らしにも取り入れやすい考え方です。
多様な環境に適応してきたチリの家づくりは、これからの持続可能な住宅デザインを考える上でも、学ぶべき点が多いといえるでしょう。
(3)チリの住宅の耐震設計の特徴
南米チリの住宅は、日本と同様に世界有数の地震多発地帯に位置しているため、非常に厳格な耐震基準が設けられている国のひとつです。
チリでは毎年約1,025回もの地震が発生し、そのうち、マグニチュード6クラス以上 の地震が年に6~10回も起こっています。
その為、チリの建物は「倒壊しないこと/命を守ること」を基本に設計され、施工者(建設業者)は法的責任を負い、不適合があれば損害賠償請求の対象となります。
建築法規(NCh433, NCh2745など)は、過去の地震の教訓をもとに随時改定されており、最新の2025年改正では産業施設向け耐震基準(NCh2369:2025)が強化されています。
さらに近年では、住宅建築にも最新解析技術や国際基準(ISO, Eurocode8等)が積極的に反映される傾向があります。
主な特徴を以下に整理しました。
■「人命保護」を最優先した設計
チリの耐震基準は「人命保護」を最大の目標としており、建物が倒壊せずに揺れに耐えることを最も重視します。
これにより、大地震の際に一部の損傷は許容しつつも、居住者の避難時間を確保し、死傷者を最小限に抑える設計思想が徹底されています。
■壁式鉄筋コンクリート造の採用
チリでは、鉄筋コンクリート造(RC造)の建物が主流で、特に壁式構造(耐震壁)による補強が広く用いられています。
これにより、建物全体の剛性(変形しにくさ)と強度が高まり、高層マンションでも大地震に耐える高い安全性を実現しています。
■最新の耐震解析技術の導入
近年の改正基準では、地盤特性や建物の応答解析(動的解析)を取り入れた設計が求められています。
特に、地盤の揺れ方に応じた応答スペクトル設計や、基礎・接合部の詳細設計の厳格化が進んでいます。
■地震後の改訂と継続的な改善
チリでは、大地震の発生後に必ず耐震基準が見直され、「地震から学ぶ設計文化」が根付いています。
たとえば、2010年のマウレ地震以降、構造耐力だけでなく復旧性(Resilience)も重視され、地震後に迅速に修復可能な設計が推奨されています。
■責任体制と法的枠組みの明確化
建築士・構造技術者・施工会社にはそれぞれ法的責任があり、基準不適合や施工不良があれば損害賠償の対象となります。
この厳しい責任制度が、設計品質と施工精度の高さを支えています。
チリの住宅は、「人命を守ること」を最優先に、「倒壊しない強さ」と「復旧のしやすさ」を両立し、「壁式RC構造+国際基準レベルの設計技術」で耐震性能を確保しています。
その結果、マグニチュード8クラスの大地震でも甚大な倒壊被害が少ないという高い実績を誇っています。
参考:
- 最新のトピックス
- 人気のトピックス